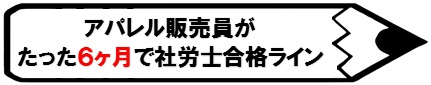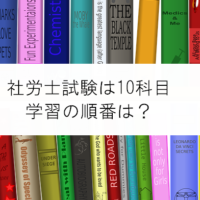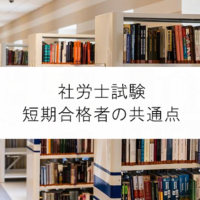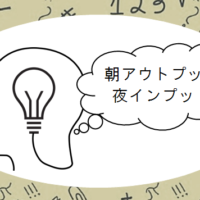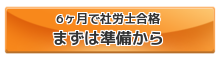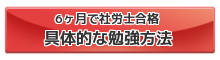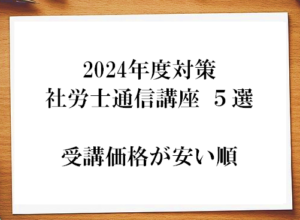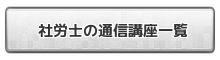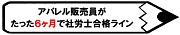![]() 本記事はプロモーションを含みます
本記事はプロモーションを含みます
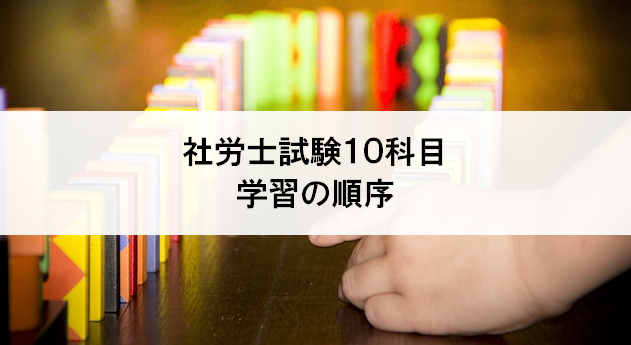
毎年、このテーマ「科目の学習順序」を配信していますが、改めて解説しております。
社労士試験は全部で10科目ありますが、適当にどれから初めても良いのではなく、効率良く進めるための順序があります。
例えば、いきなり厚生年金科目から取り掛かる…これは効率がかなり悪く、やっても理解できないと思うのでNGです。
必ず最初は労働基準法からスタートしましょう。
スポンサーリンク
社労士試験10科目 学習の順序について
社労士試験科目は全部で10科目です。
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労災保険法
・雇用保険法
・徴収法
・労務管理その他労働に関する一般常識
・健康保険法
・国民年金法
・厚生年金保険法
・社会保険に関する一般常識
教材となる入門テキストや基本テキスト、更に過去問でも上記の順に掲載されていることが多いはずです。
そして色分けしていますが、赤色が労働関連法、青色が社会保険関連法となっています。
つまり、社労士試験の科目は大きく2つに分類できます。
徐々に理解を深めていったり、各法令が関係しあったりしているため、上記が一般的な順番となっています。
効率良く学習するための順番
最初は労働保険科目からですが、その中でも労働基準法が最初にやる科目となります。これは絶対です( ゚Д゚)
順番に進めていくのには意味があり、科目別に見ると以下のプロセスで学びます。
・労働基準法(労働関連法の基礎)
・労働安全衛生法(働く場所の具体的なルール)
・労災保険法と雇用保険法(労働者の権利補償、救済)
・徴収法(労災・雇用の保険料徴収)
労働基準法で基礎を知り、そこから各科目の詳しい法令、それらの保険料徴収についても知識を学ぶという流れです。
いきなり労災保険からやっても意味不明なのは分かりますよね。
社会保険科目も、健康保険法から始まりますが、これは歴史が古い法律から学び、年金制度のベースとなる国民年金から年金制度の2階部分となる厚生年金保険へと学びを進めていけるようになっています。
どういった順番で進めていけば良い?という事に対しては、上記の順が最も効率が良いと思います。
各法律が関係しあっている
先ほども「各法令が関係しあっている」と言いましたが、そうなんです。
基本テキストを1周すると、理解できない科目が出てくると思います。
このときは、分からないからといって長い時間立ち止まらず、とにかく前へ進みましょう。
社労士試験の科目は名称が違えど、各法律同士が相互に深く関わりあっているため、順を追って他の法令等との関連性で理解できるケースもあります。
分からないところで立ち止まっていると、横断的な理解が進まず、結果的にペースが遅くなるので、まずは各科目まんべんなく、浅く広くを念頭に、理解できなくてもとにかく前に進んでください。
そのためにも科目の学習順序は重要となります。
一般常識科目は2パターン
そして忘れてはいけない一般常識2科目(労働一般・社会一般)ですが、この科目の取り入れ方については2パターンあります。
「労働保険科目が終わって労働一般、社会保険科目が終わって社会一般」
「最後に一般常識2科目をまとめてやる」
私の場合は後者でしたが、前者でも問題ありません。
ただ、ここでは実際に私がやった学習方法で解説しているので、後者のパターンで解説していきます。
後者のパターンでは、
・労働保険科目
・社会保険科目
・一般常識科目
この3つに分類して学習を進めていくスタイルになります。
私がこれにした理由として、
・労働白書や統計など、基本テキスト以外から情報収集が必要になるから
・後半に一般常識に特化した専用テキストで強化するため(通信でも一般常識対策としてまとめられているため)
・それぞれの一般常識以外の科目は基本となっているため、知識が混同しないため
一般常識科目は白書なども含まれるため広範囲に及びます。
そのため、つい後回しになりがちですが、後者の順でやる際は疎かにしないように、他の科目と同様のモチベーションで進めていきましょう(^^;
実際に私がやった順番
ということで実際に私がやった社労士試験科目の学習順は以下の通りです。
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労災保険法
・雇用保険法
・徴収法
・健康保険法
・国民年金法
・厚生年金保険法
・労務管理その他労働に関する一般常識
・社会保険に関する一般常識
最後に一般常識科目をまとめてやり、大きく3分類で学習を進めていきました。
対策が難しい一般常識は専用テキストや通信講座の単科講座で対応するなど、何等かの対策が必要になるかと思います。※白書は概要版も活用しましょう。
これとは違ったもう一つの順番でも構いませんが、最初にどちらのパターンで進めていくかを決めておいた方が効率が良いかと思います。
以上、参考までに
当サイトで推奨の社労士講座フォーサイト
2024年度対策 開講中!
詳しい割引価格や教材は公式へ↓↓