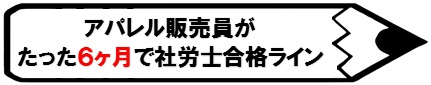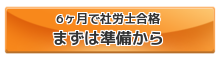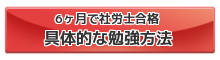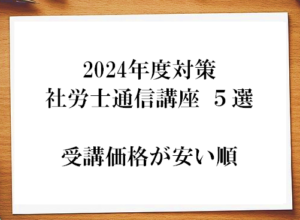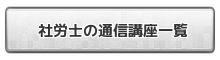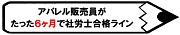![]() 本記事はプロモーションを含みます
本記事はプロモーションを含みます
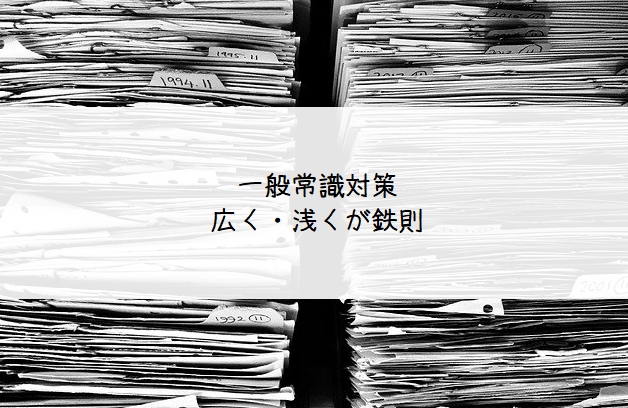
社労士試験は10科目、その内2科目は一般常識があります。
労務管理その他労働に関する一般常識
社会保険に関する一般常識
これら2科目は他の主要8科目とは異なり、とにかく範囲が広いです。
法令だけでも多いうえに、白書対策も入るのでなかなかのボリュームです。
なので、短期間で完璧に覚えきるの事は、恐らく不可能に近いかと思います。
では捨てるのか…いや、捨てません、というか捨てれません( ゚Д゚)!
科目別の合格基準があるので、必ず対策は必要になります。
この対策方法ですが、実は他の主要8科目よりシンプルです。
出題されるところがある程度絞り込まれており、過去問での問題演習を中心にアウトプット学習を進めていけばOKです。
一般常識科目の法令は多岐にわたりますが、中でも講義メディアや基本テキストで学習するものに注力すれば良いでしょう。
それ以外やってしまうと沼…キリがないので、過去に出題されたもの、基本テキストに掲載されている法令を中心に学習します。
基本テキストもしっかりした教材のものなら、過去問とリンクしてあるはずなので、最低限押さえるべき重要なポイントは分かりやすいと思います。
これが完全独学となると、これまた大変なのです(^^;
通信講座や予備校などの教材を推奨します。
そして白書対策や法改正です。
これらは毎年変わるので、昨年通り覚えるのではなく、最新の数字等をチェックしておく必要があります。
前回も配信しましたが、白書対策としては「概要版やリーフレット」を中心に対策するのがおすすめです。
ガチの白書を見ると、あまりのボリュームにやる気がなくなります。
概要版などは、厚生労働省(国)が知ってほしいこと、重要視していること、その中でのポイントを中心に掲載されます。
つまり、試験を出す側としても使いやすいものなのです。
私も白書に関しては概要版をチェックしていました。
スマホでも簡単に誰でも見れるので、スキマ時間などを活用して読んでおきましょう。
一般常識科目では、基礎知識、白書統計を含め、深入りはNGです。
基礎知識を講義メディア、基本テキストで押さえておき、白書統計は概要版や過去に出題されたポイントを中心に学習します。
広く・浅く…これは鉄則です。
深入りしすぎると他の主要科目にも影響が出ますし、マニアックなところまで学習する必要はありません。
範囲が広いため、どうしても後回しになりがちな一般常識科目ですが、この2科目によって合格に届かない受験生が結構います。
特に労働一般、これは厄介ですので、対策は必須です。
これまでの社労士試験の平均点を見ても、労働一般は特に低めです。
対策としてはシンプルなのですが。やはりこういった学習すべきポイントや白書統計対策は、独学ではなく専用テキストや通信講座、予備校の力を借りるのが得策でしょう。
通信講座なら単科でも利用できるので、効率良く学習を進めていきましょう。
一般常識・白書統計対策
社労士講座フォーサイト
詳しい教材、割引価格、お申込は公式サイトへ↓↓