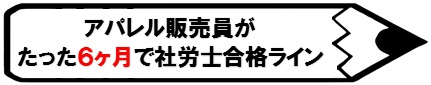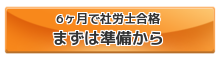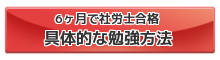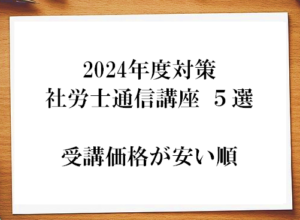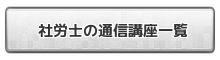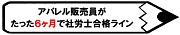![]() 本記事はプロモーションを含みます
本記事はプロモーションを含みます
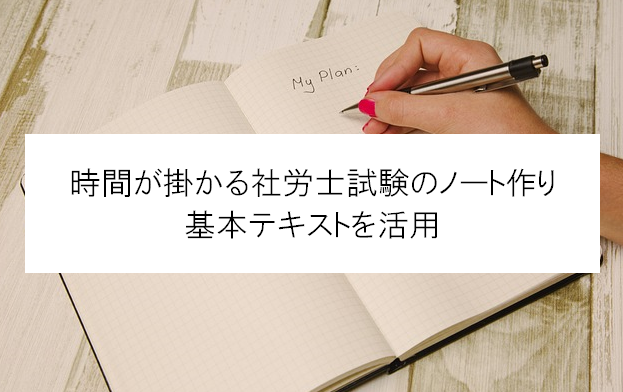
社労士試験対策として、独自にまとめたノートを作るべきかについて、私の場合はこういったノートは作成しませんでした。
わずか6ヶ月という期間で合格を目指していたので、どうしても時間のかかるノート作りはスルーしました。
とはいえ、独自のまとめノートを作ること自体、意味が無いわけではないと思います。単に時間が無かっただけで作らなかったので、もし1年くらいの学習期間があれば作っていたかもしれません。
「自分の分からない箇所を中心にノートにまとめる」これは最終的な直前対策や試験前にチェックするのに効果的かと思います。
私の場合、全く何もしなかったという事ではなく、ノートではなく基本テキストへの書き込みを行いました。
ノート作りに必要以上に時間を取られるのは得策ではないので、すでにまとめてある基本テキストに必要な情報を書き込む感じです。
基本テキストには必ず余白があるので、ここを使います。
私の学習方法では分冊もされているので持ち運びも便利、この中に必要な情報がすべて網羅されていれば直前対策や試験当日も持ち運びしやすいかと思います。
※もちろんそれでもノート派の方はノートでもOKかと思います。
で、何を書き込むのか分からない場合、以下のポイントを中心にチェックしていくと良いでしょう。
・理解がイマイチできない箇所
→この部分はテキスト以外から知識を調べます。例えば講義メディアやインターネット、講座の質問サービスなどを利用して独自に分かるように書き込むを加えます。
・文章だけでは分かりにくい箇所
→図表などを組み合わせて書き込みます。
・法改正事項
→社労士試験対策として法改正は重要項目です。当サイトでも紹介していますが、そのテキストが公開している法改正情報をプリントアウトし、ハサミなどで切って法改正の箇所に貼り付けていきます。法改正前の情報も確認できるので、何がどう変わったかも確認できます。
・白書統計対策の数値
→ここは最新の数字が重要なので、古い情報をアップデートすればOK、覚える数字は少しでも省いていきます。
・過去出題箇所
→これも当サイトで何度も紹介していますが、過去問とリンクさせます。過去問で出た箇所をマーカーなどでチェックすることで、その周辺箇所も注視して学習できます。最初は時間がかかりますが、一度やればそのあとは読むだけなのでおすすめです。
このように、独自のノートを作る方法もありますが、私の場合は基本テキストへの書き込みを使って少しでも時間を削減しました。
基本事項はすでに書かれていますし、必要な情報だけ加えれば済むので、短期合格を目指す際は参考にしてみてください。
効率よく合格を目指す
社労士講座フォーサイト
詳しい教材、割引価格、お申込は公式サイトへ↓↓